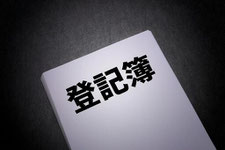会社の実情に合わせて定款を作り直す
すでに会社を設立された方、定款はどのように管理していますか?
設立時からなんら変更なく、放置したまま金庫に眠っていませんか?
会社法施行後、大きく定款ルールが変わったことをご存知ですか?
【会社法施行後の定款】
平成18年5月1日より新会社法が施行されました。
整備法により施行日以降は、既存の株式会社は、会社法の規定による株式会社として存続するものとされ、定款に関して、旧株式会社の定款は、「新株式会社の定款とみなす」と規定されました。
有限会社においては既存の有限会社が廃止され、「特例有限会社」が、会社法上の株式会社として存続するとされました。
基本的に、既存の有限会社は登記を申請する必要もなく、登記官の職権登記によって登記簿上は「特例有限会社」に移行しています。
また、定款においても多くの、みなし規定が置かれています。
これまでの旧商法時代では、株式会社においては、会社の組織や規律は統一的に法律で規制されていたため、どの株式会社の定款を見ても似たり寄ったりな内容の定款でした。
以前の会社設立では、商号と本店を入れてほぼ完成してしまう市販の定款ひな型でも事が足りていたわけです。
しかし、新会社法では、「定款自治」といわれるように、法律の規制は最小限にとどめ、定款に定めることによって会社の実情に沿った企業運営ができるようになっているのです。
そして役員変更登記は、定型的で簡単なものから、場合によっては役員の実印や印鑑証明書、会社代表印の再登録などが必要なものまで様々なバリエーションがあるのです。
【定款の見直し・カスタマイズ】
登記事項に関する定款の決め方、変更手続きは各変更登記のページをご覧ください。
ここでは、それ以外の定款記載事項で見直しをしておいたほうがよいと思われる内容をご紹介します。
1. 会社の機関設計の見直し
新会社法施行前、株式会社を設立するには、取締役は必ず3名以上、監査役も必須、取締役会も必ず設置されていました。
新会社法以前に設立された会社は、自動的に取締役会設置会社、監査役設置会社と登記されています。
ところが現在は、取締役は1名でも可能、監査役を置かなくても可能になっており、自由な機関設定が可能になっています。
従前、会社を興すために人数合わせのためだけに取締役や監査役になってもらうこともあったと思いますが、現在はそのような必要もなく、会社の実情に即した役員構成が可能です。
具体的には、
| 非公開会社 | 公開会社 | |
| 大会社以外 |
1.取締役のみ 2.取締役+監査役(会計監査) 3.取締役+監査役 4.取締役会+会計参与 5.取締役会+監査役(会計監査) 6.取締役会+監査役 7.取締役会+監査役会 8.取締役+監査役+会計監査人 9.取締役会+監査役+会計監査人 10.取締役会+委員会+会計監査人(委員会設置会社) 11.取締役会+監査役会+会計監査人(監査役会設置会社) |
1.取締役会+監査役 2.取締役会+監査役会 3.取締役会+監査役+会計監査人 4.取締役会+委員会+会計監査人(委員会設置会社) 5.取締役会+監査役会+会計監査人(監査役会設置会社) |
| 大会社 |
1.取締役+監査役+会計監査人 2.取締役会+監査役+会計監査人 3.取締役会+委員会+会計監査人(委員会設置会社) 4.取締役会+監査役会+会計監査人(監査役会設置会社) |
1.取締役会+委員会+会計監査人(委員会設置会社) 2.取締役会+監査役会+会計監査人(監査役会設置会社) |
株式の譲渡制限規定を置いている会社を非公開会社、そうでない会社を公開会社といいます。
非公開会社では、株式を譲渡するときに代表取締役や株主総会、会社等の承認を必要としますので株主の分散を防止するためには必ず設定します。
中小企業の多くは、非公開会社ですから、上記のようなシンプルな機関設計が可能です。
機関設定を変更することで、役員がかけた時に名目上の役員を探して取締役に就任してもらったりする無駄な仕事もなくなり、これまで役員全員の実印が必要だったわずらわしさもなくなります。
会社の実情に合わせて、役員を自分一人にして身軽にしたり、公開会社から新たに非公開会社に変更したうえで、役員を一人にすることも可能です。
役員の任期の見直し
これはご存知の方も多いかと思います。
非公開会社の場合、取締役監査役の任期は10年まで伸ばすことが可能です。
従来は取締役2年、監査役4年という任期が原則であったため、2年、4年ごとに役員変更登記をする必要がありましたが、定款を変更して任期を変更すれば変更登記の煩雑さから解放されます。
ただし、その分任期途中で役員を外したい場合には、辞任していただくか、解任手続きが必要になります。
役員の任期は登記事項ではありませんので、株主総会の決議で変更できます。
株券発行の定めの廃止
株券に関しては新会社法では旧商法と取り扱いが反対で、株券を発行しない会社が原則となりました。
現在会社を設立する場合、定款で定めた場合にのみ、株券を発行することができます。
新会社法前に設立された会社で株券不発行の登記がない会社は、自動的に株券発行会社として登記されています。
しかし、中小企業で実際に株券を発行している会社は少なく、今後登記の際に株券提供公告等の手続の煩雑さなどを考えると、株券発行の旨の登記を廃止したほうがよい場合もあると思います。
株式の譲渡制限
「当会社の株式を譲渡により取得するには株主総会の承認を受けなければならない。」
一般の中小企業のほとんどが株式譲渡制限会社でしょう。
株式を譲渡するには会社の承認が必要である定めのことで、登記事項です。
承認機関は株主総会でも、代表取締役でも構いません。
株式の分散を防ぎ、会社の経営を安定ものにするための必須の規定です。
相続人に対する株式の売り渡し請求
「当会社は、相続その他一般承継により等会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。」
株式の分散の原因として相続があります。
遺言で株式の帰属を定めておくことも重要ですが、遺言がなく相続によって株式が分散する恐れがある場合有効な定めです。
その他文言修正
新会社法によって単純に文言が変更されている箇所もあります。
登記のご依頼をいただいたとき、あまりに古い定款を持ってこられると昔の記載のままになっています。
取引先等に提出を求められたとき、あまりに古い定款のままの状態で持っていくのはいかがなものかと感じます。
やはり、単純な文言の変更であっても、常に新しい法律に対応しておいたほうがよろしいのではないでしょうか。
たとえば、
|
従来 |
新会社法 |
|
発行する株式の総数 |
発行可能株式総数 |
|
営業年度 |
事業年度 |
|
利益配当金 |
剰余金 |
定款変更・カスタマイズのご相談について
たとえば、よくあるご相談で、従前の公開株式会社を実情に即したコンパクトなものに変更したいというものがあります。
具体的には定款変更を行い、
1.株式譲渡制限会社に変更
2.取締役会の廃止
3.監査役の廃止
4.取締役の人数を最小限に変更、任期を10年に変更
5.株券発行会社である旨を廃止
6.必要に応じて役員変更、商号目的変更、本店移転
7.その他文言等所要の変更
等を一括して行います。
まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談には会社の登記事項証明書、定款、株主名簿をご持参ください。
(ご依頼の流れ)
1.ご相談・御見積
2.ご依頼・定款変更案、必要書類作成
3.株主総会サポート可、必要書類への押印・ご本人様確認・費用お支払い
4.変更登記が必要な場合登記申請
5.登記完了後、登記事項証明書、新定款のお渡し、お預かり書類のご返却
よくある定款変更の事例紹介
たとえば、よくあるご相談で、従前の公開株式会社を実情に即したコンパクトなものに変更したいというものがあります。
具体的には定款変更を行い、
1.株式譲渡制限会社に変更
2.取締役会の廃止
3.監査役の廃止
4.取締役の人数を最小限に変更、任期を10年に変更
5.株券発行会社である旨を廃止
6.必要に応じて役員変更、商号目的変更、本店移転
7.その他文言等所要の変更
等を一括して行います。
まずはお気軽にご相談下さい。
ご相談には会社の登記事項証明書、定款、株主名簿をご持参ください。